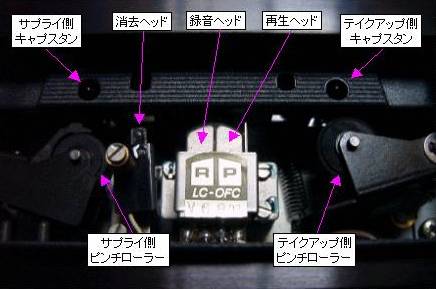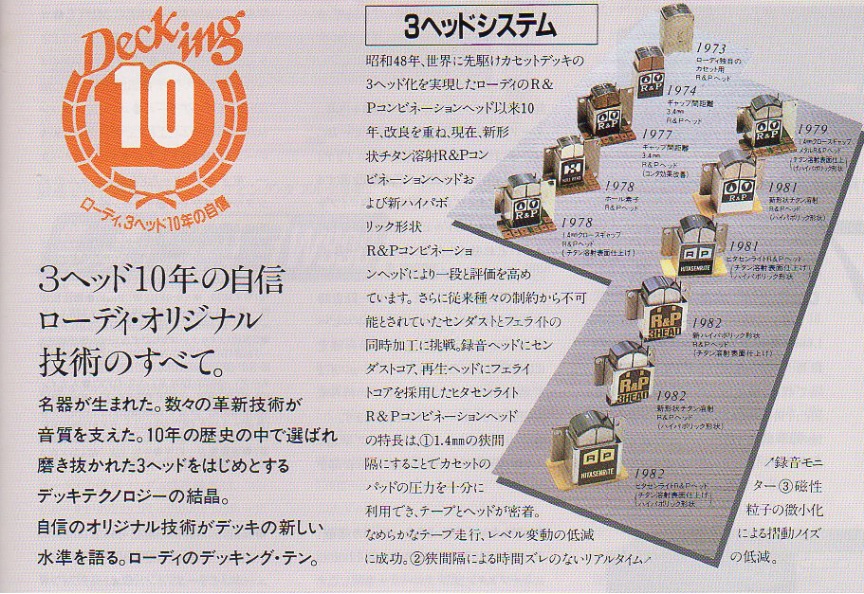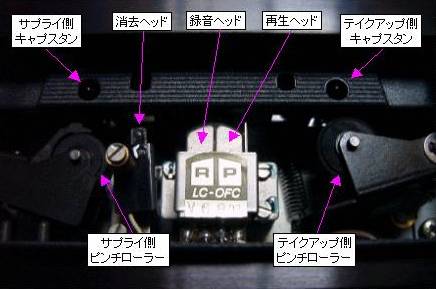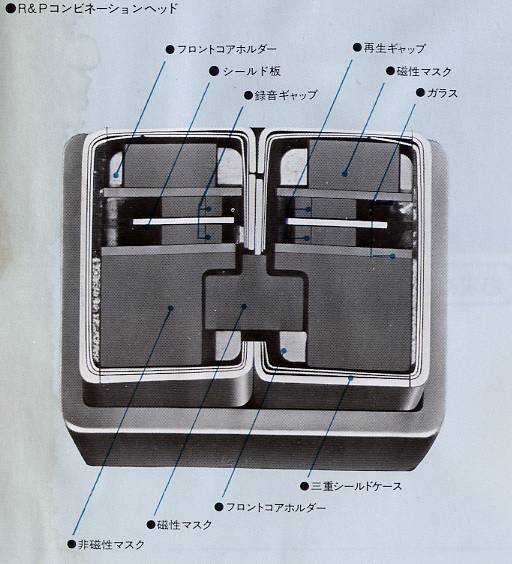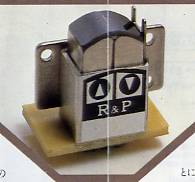コンビネーション 3 ヘッド
~CLOSE GAP Rec&Play~
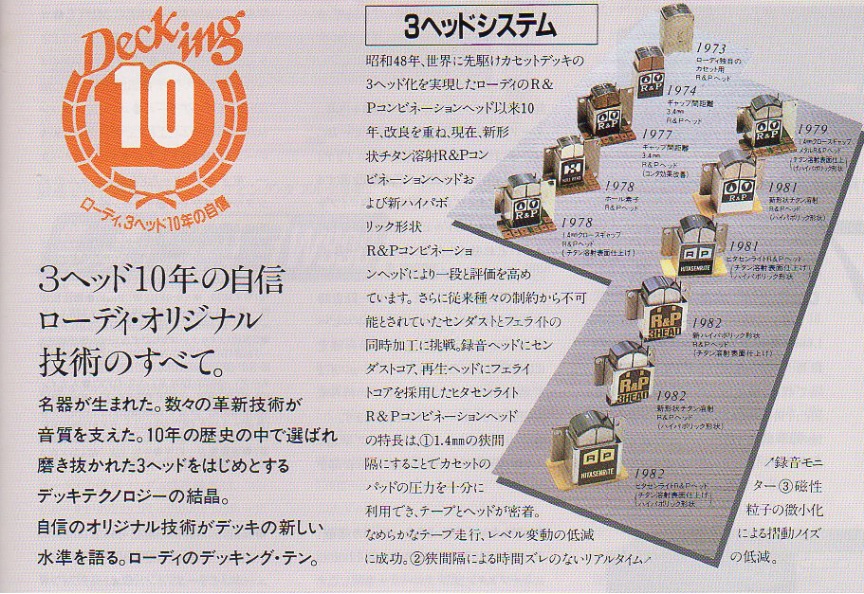
3 ヘッドとは、テープに記録されている情報を消去するための消去ヘッド、テープに音を磁気信号として録音するための録音ヘッド、およびテープに記録された磁気信号を読み出して再生する再生ヘッド
が、それぞれ独立しているヘッド方式を言います。一般的なデッキは、録音再生の役割を兼用させ、消去ヘッドと録音再生ヘッドの 2 ヘッドとしているのが普通です。また、再生専用でしたら 1 ヘッドということになります。
元々、録音と再生は相反するものであり、ヘッドの構成もそれぞれの理想が異なります。よって録音再生兼用の2ヘッド方式では、お互いの妥協点でヘッドを作ることになります。3 ヘッド方式は
まさに磁気記録方式のカセットにとって理想とする構成ですが、カセットテープのハーフの構造上それを
実現するのは困難と言われていました。
そこへ、録音ヘッドと再生ヘッドを別々としながらも、見かけ 1 つのヘッドになるように組み合わせ
(このことからコンビネーション型と言われる)ることで、世界で初めて 3 ヘッドを実現したのが
ローディでした。3 ヘッド方式には、このコンビネーション型と、ほぼ同時期にナカミチが発表した
完全独立型 3 ヘッドがあります。これ以降のカセットデッキでは、コンビネーション型が主流になりました。
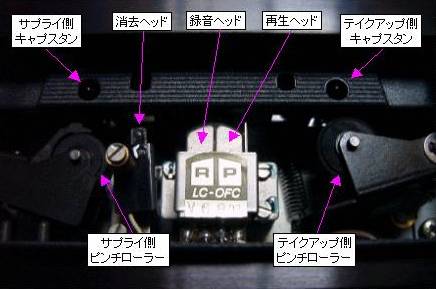
コンビネーション型 3 ヘッドの位置関係(クローズドループデュアルキャプスタン方式での例)
ローディが初めてコンビネーション型3ヘッドを搭載したのは、1973 年(昭和 48 年)発表の D-4500 というモデルでした。当初は音質向上のための 3 ヘッド化はもちろんのこと、失敗の許されない
録音で、安心して録音状態が確認できる、いわゆる録音同時再生モニターができることも大きな
特徴として謳われていたようです(当時の資料より)。性能的には、
・同一歪率では従来の再生・録音兼用ヘッドに比べて、再生出力は 2dB 以上向上
・周波数特性をひずみなく伸ばすことに成功
・録音側から再生側へのクロスフィード(漏洩磁束)はノイズレベル以下に抑制
・高密度フェライトにより耐磨耗性に優れ、再生ヘッドは 1.0μm ギャップ、録音ヘッドは 4μm
とし、理想の独立専用設計
といったところが紹介されています。
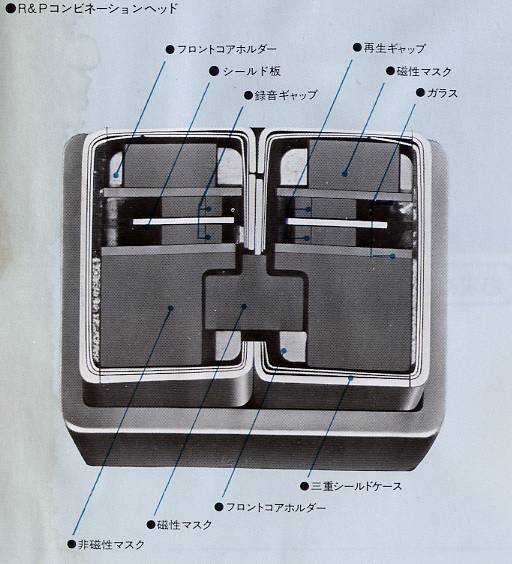
当初のコンビネーションヘッドの構成
その後、最初の資料のような数回の改良が行われながら、最終モデルである D-707HX まで搭載されました。ローディの3ヘッドが他社のヘッドと大きく異なるのは、その形状と表面仕上げです。録音ヘッドと再生ヘッドのギャップ(距離)を1.4mmと極めて狭くしたこと、および
表面をチタン溶射し、鏡のように鏡面仕上げすることでヘッドとテープの接触性を高め、
レベル変動の低減・テープが走行することで発生する雑音を低減しています。
ヘッドそのものの素材としては、高飽和磁束密度フェライト材を採用していました。その間にも、
ホール素子、ヒタセンライトといったようなものもありました。詳しい資料を持ち合わせていないので
詳細は分かりませんが、ホール素子は外部磁界によって起電力が発生する素子であり、再生側に
利用されていたことが分かります。ヒタセンライトは、
「オーディオ回顧録《のホームページ
の D-2200MB の中で紹介されていますので参照ください。
ヘッドの表面形状も順次改良されていきます。最初は、他メーカーのヘッドと同様の
形状ですが、1979 年にハイパボリック型になっています。これによりテープとの接触面積を
小さくでき、接触性を高めることができます。最終型は、これがもう少しなめらかに
なり(新形状チタン溶射 R&P )、レベル変動の低減に成功しています。なお、
新形状チタン溶射の変り種として、D-8 にのみ搭載された V 溝ヘッドがあります。
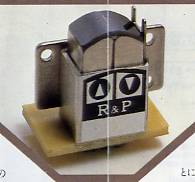
1981年 新形状チタン溶射 1.4mm クローズギャップR&Pヘッド
また、D-707Ⅱ および D-707HX には、ヘッドの巻線に LC-OFC 材を使用しています。
LC-OFC(Linear Crystal-Oxygen Free Cupper) は、日立電線が開発した銅の結晶構造を直線配列させた
無酸素銅で、音質向上に有効な素材とされています。更に、ヘッドベースの空間部分に、
ブチルゴムを主成分とした振動減衰材を充填し、振動を軽減する処理がなされました。
これが、ローディの 3 ヘッド開発の集大成となったのでした。